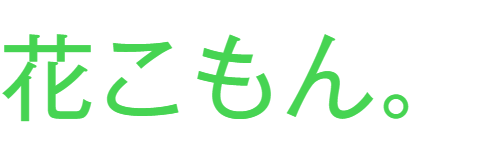出光美術館の岩佐又兵衛と源氏絵を観ました。
会期はおわってしまいますが
思うことの多い展覧会でしたので
率直な感想をつづってみたいと思います![]()

こんなふうに皇居をすぐ目の前にして源氏絵を観られるのは贅沢なこと![]()
源氏物語は今でこそ、たくさんの現代語訳があり、漫画にもなって、
女子高生でさえ どのヒロインが好きだとか自由自在にお喋りできる
国民全体で共有する文学となっていますが
それも実は昭和の後半以後のことなのだそうで
戦前などは皇室に関わりあるこの小説にはいろいろな制約がありましたし、
時代をずっとさかのぼれば、中世までは完全に高貴なクラスだけに
閉ざされていた特別な文化でした。
教養というものは、それを持つ人に権力は与えないけれども
権威を与えます。
鎌倉以後、武士が政権を持ち続けた日本にあって
天皇家や貴族が権威を保ち続けた要因の一つに古典知識がありました。
やんごとない人々から下ってくることがほとんどなかった
源氏文化の流れが大きく変わったのは江戸時代です。
そうした萌芽のひとつ
歴史の転換点に出光美術館で出逢いました。
岩佐又兵衛とその工房が描いた源氏絵です。
はっきり言ってしまえば私は土佐派の源氏絵のほうがずっと心になじみました。
抵抗なくすーっと入ってきますし、見るだけでホッとする。
やはりこれが本流です![]()
岩佐工房が源氏物語の本質をどこまで捉えているのか?といえば
ときに疑問に思う絵もあります。
花宴図で源氏が朧月夜を抱きすくめる様子をクローズアップして描く
俗っぽい感じなどはかなり抵抗がありました。

花の宴の巻をあえて描くなら、この場面ではないと思う・・・
王朝の雅とは隔たったものを感じました。
ですが一つ断言できることがあるとすれば
岩佐工房が描いた源氏絵は日本の歴史になくてはならないものだったろうということ。
実際、あの扇情的な花宴図は描かれた枚数から推察してみても
当時結構な評判を得ていたことがわかります。
それが浮世絵の元祖である、という存在意義だけではなく、
江戸時代の源氏研究のゆたかな発展や
源氏物語が大衆化し、真の日本の古典となる動きと、
この美術の動きはけっして無縁ではないからです。
高貴な知識人たちに近い土佐派では生み出せないオリジナリティーは、
源氏文化にあたらしい命を確かに吹き込んでいます。

ポスターにもなっている賢木の巻の絵はさすがにステキです。
これは色鮮やかなものより、むしろこうした水墨主体で描くほうが
いっそう趣き深いかもしれません。
一場面だけを切り取っていることも新鮮で、
岩佐又兵衛のたしかな “ 華 ” がここにあります![]()
型を継承していくスタイルを軽々と超えていけるのは
異文化を土壌にしている者の強みでもあるでしょう。
若菜の巻で女三の宮の猫が御簾を引き上げてしまって
柏木や夕霧が彼女の可憐な姿を目の当たりにしてしまうシーンがありますが
それが岩佐勝友の「源氏物語図屏風」では
なんと三の宮自身が自力で御簾をよけ、
堂々と顔をのぞかせているんですよー
もうかなり笑えます。
笑いを狙ったのか、単なる知識不足なのかはさっぱりわからないのだけど・・・
川柳など古典に笑いをもたらす余裕が江戸時代一気に花ひらきます。
優雅な世界を身近な日常に落としこむ動きも、江戸文学には見られます。
そうした兆しが今回あちこちにみられ、
歴史上の出来事とか芸術の評価なんて何百年というスパンで
見なくてはわからないと思いましたし、
世の中って、人間って、歴史って
ほんとうにオモシロイと思った美術鑑賞でした。
優雅にして野卑な岩佐又兵衛。あきらかに歴史に選ばれたスターでしょう。
そんな時間と空間と出来事と人々とを見渡すように思いをはせ、
わたしの心はすごくわちゃわちゃしました~。
今回も言葉にならない神秘的な気づきをたくさん得た気がしています![]()
![]()